1/27の16時から1/28の2時過ぎまで続いた、フジテレビの会見について会議の視点で学べるポイントを挙げてみます。ご存知の無い方は、ネットでアーカイブがあると思いますのでご視聴をおススメします。なお、会見を評価する内容ではありませんのでご承知おきください。
会見動画の一つとしてYoutube ReHacQ リハックチャンネルの動画をご紹介しておきます。
コチラ

こんにちは、当サイト(ワクワク会議研究所)の所長です。私は企業団体の会議に10年間取り組み、今は企業の会議改善コンサルタントをしています。しかしその過程では、有意義な会議を開催できるようになるまで沢山の失敗と学びを重ねてきました。
会議の工夫が難しい点の一つに、客観的に観察や分析をしにくいということがあります。多くの場合無関係な会議に参加することがないからです。今回の会見と当サイトの会議は厳密には違うものですが、そこに表れる関係性や意見のキャッチボールには学びとれるものがあります。取り入れてみてはどうでしょうか。

10時間を超えるどえらい長い会見でしたね。
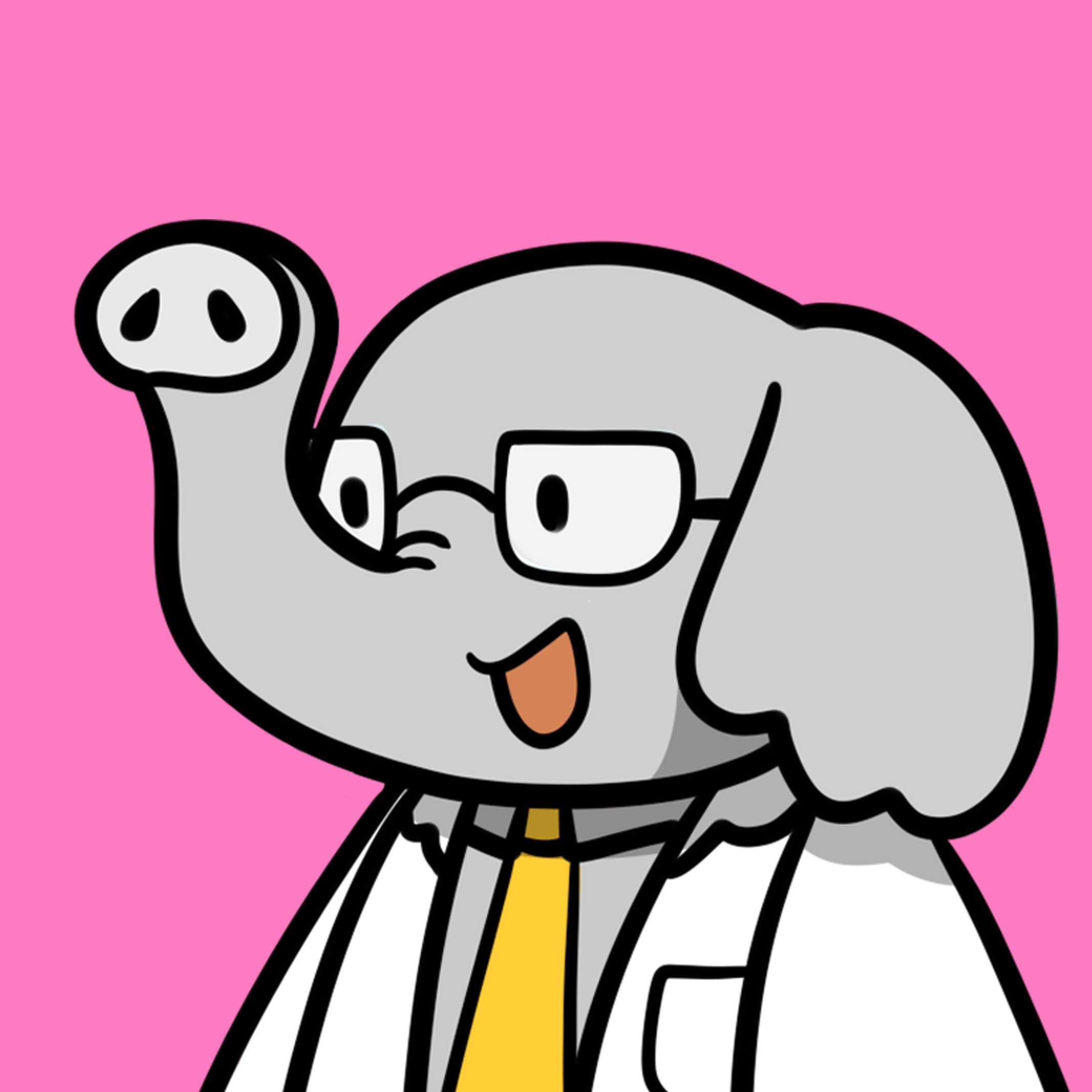
10時間以上かかってしまった、とも言えるし10時間以上かける必要があったとも言えるね。それによって誰が何を得たのか考えてみても面白いね。
ともあれ、国内の名だたる企業での意見交換が俯瞰で見れるからこんな機会は逃せない。是非ポイントを見てみよう。
ピックアップポイント
・質問者の質問の投げかけ方(感情 内容の精度 越権の姿勢)
・司会者の選抜と進行スキル
・質問者ができること
・本質的な目的
前提
会の目的:情報のやり取りを通じて、参加者各自が目的を果たす
参加者カテゴリー
登壇者:役員5名
司会者:1名(フジテレビ社員)
質問者:約100名(フリー記者含む)
参加者カテゴリーの目的(仮定)
登壇者:誠実さを示しつつ、不必要な情報提供をせずに質問がなくなるまで開催しきる
質問者:欲しい情報を引き出す
司会者:出来る限り登壇者、質問者にとって質の高い時間になるよう適切に介入する
全体的な印象
SNSの投稿やYoutubeのコメントから視聴者の感想を拾うといまいち核心に迫れず、登壇者、質問者、司会者それぞれに対し不満を抱いた方々が多いようです。良い質問ができて、良い返答が得られた時間であれば不満を持たないのでまとめると、情報のやり取りが円滑ではなかったと言えます。
では、冒頭の繰り返しになりますが、会議に当てはめて考察していきます。
質問者の質問の投げかけ方
感情
質問者の内容、姿勢はさまざまだったのですが、特に場を乱し目的から遠ざかる要因となったのは、感情的な投げかけをする質問者数名です。
感情が乗っかった質問は、言語スキルで表現しきれない分を感情に変換してしまっていると認識できます。
その対応として、登壇者は冷静にうなずいていました。となると構図は真摯に対応する余裕を示した登壇者、余裕のない質問者になるので内容に関わらず、登壇者優位になります。
また、質問ではなく主張になっている状況もありました。特に、感情の乗った主張となると自分の思いをぶつけて、納得のいくリアクションを得たいという心理が現れるので、一方的に感情で殴りにかかっている姿勢とも取れます。

勢いのある方が優勢なのかと思ってました。
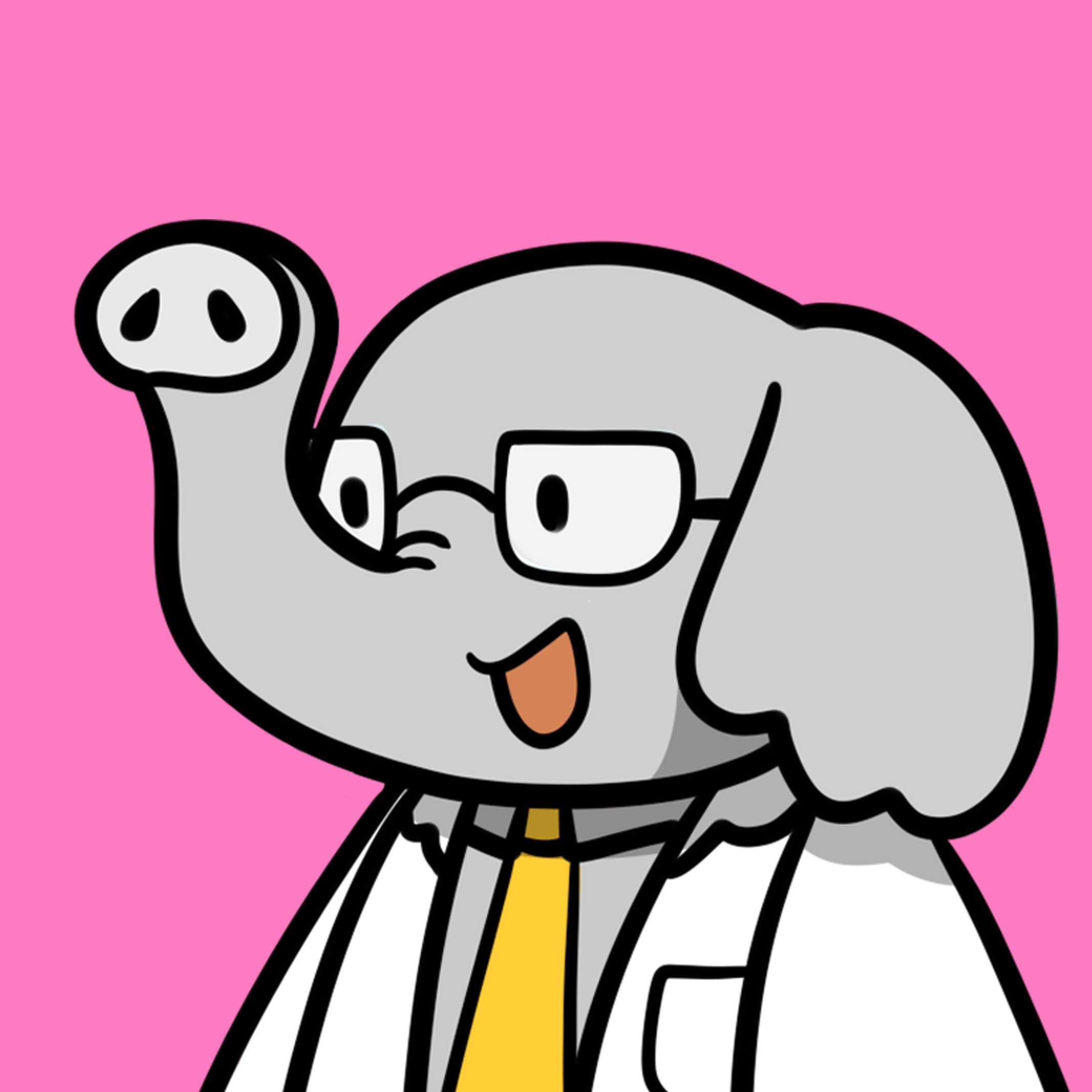
もちろん、その側面もあるよ。でも人は社会的な動物だからモラルの範囲内で振舞う事も大事だよね。フジテレビ側のモラルを追求する際に、追求側がモラルを逸脱しちゃぁ身も蓋もないよね。
ご自身の会議に紐づけるなら、発言者の感情に意識を向けてみると話し合いの流れや雰囲気の元が感じられるようになるでしょう。
また、感情的な発言者がいる場合の対処として考えられるのは、まず感情とその背景の考えを意見として受け止め、冷静さが保てた状態で内容を取り上げるかどうか検討するとういうことです。
内容の精度
続いて、質問者の投げかけた内容についてです。基本的に人に質問を投げかけるときは、単刀直入な投げかけ方をした方が相手が受け取りやすく、つまり返答もしやすくなります。複雑なものはその後に続けて補足として加えれば良いわけです。
文章でいうなら、短い文にして「。(句点)」で区切っていく。そして結論を先に伝えるという形になります。
ところが今回の質問者の中には、そのようにできず
- 何が結論かがわかりづらい人
- 一つの発言が長い人
- 「えー」「あのー」などの言葉が間に入り聞きづらい人
が多くいました。考えを進めながら発言しているとそうなります。
基本的に人は思考に負担が少ないものを好みます。商品キャッチコピーや選挙のワンイシューを想像していただくと分かりやすいのではないでしょうか。

たどたどしくても質問者の率直な感じがあっていいのかと思いました。
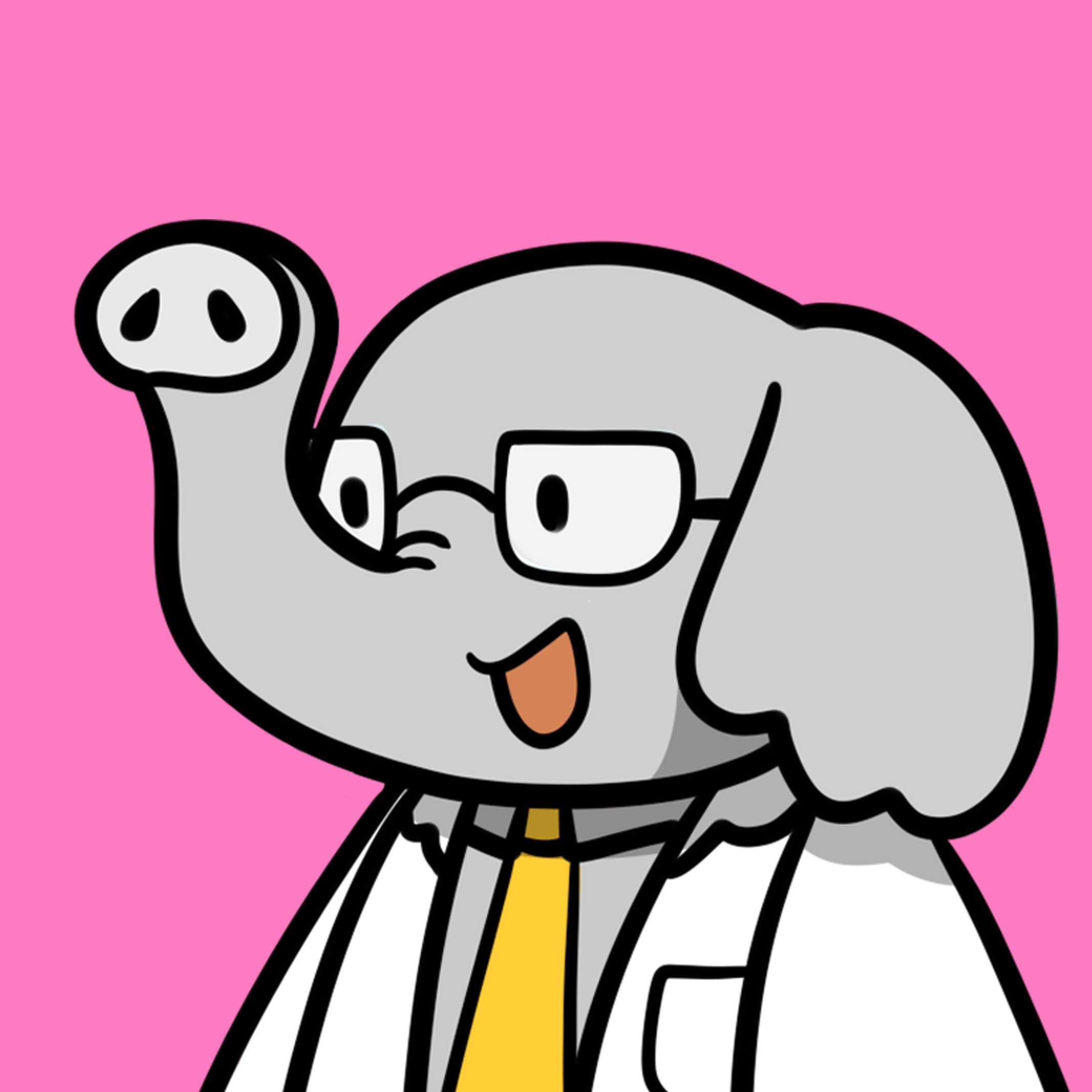
ダメ、というよりは、返答を引き出す目的からすると上手くないって感じかな。
なので、発言者の内容をよく聞き取らなければいけないと言うことが起こると登壇者は曖昧な返答になりやすいですし、聞き取っている間の姿勢が謙虚、真摯であれば登壇者優位の構図になります。
会議に置き換えて考えると、質問者としてできる事は、事前に自分が聞きたい事は何なのかを明確にして、相手の返答もある程度予想した上で投げかける言葉を的確に選んでおくことになります。
会議の場合は議論が反れたり、付随する重要議題が発生すると言うこともあるので臨機応変にやりとりをしなければいけないこともあります。その時は非常に難易度の高い状況ですので、普段から意見の明確化、簡潔化を意識しておくことで、臨機応変な対応力を鍛えることができます。
越権の姿勢
会見の途中で司会者に対して、司会は黙っていてくれとか、司会は変わったほうがいいとか、進行役に対するネガティブな発言がありました。司会はその発言を受取り、次にどうするべきか困ってしまったために即座にレスポンスができず、矢継ぎ早に発言者の主張や他者のヤジも飛び交い一時的にカオスな状態にまで進んでしまいました。
司会者に実力不足の側面はありますが、一方で質問者の、役割を超えて自分が場を仕切ろうと言う姿勢は、いかなる時も他の参加者に受け入れられる事がないでしょう。おそらく、当人も自分が司会を変わろうと思っていたというよりは、司会者や登壇者に対する否定の姿勢を示したかったのだと推察します。
また、自分がマイクを持っていないのに(そのタイミングで発言権がないのに)発言をし始める人もいました。本人にとっては自分の主張を受け取ってくれという姿勢になるわけですが、裏を返せば、平等に発言権がある他の人の権利を差し置いて、自分を大切にしろということでもあり、傲慢の表れになっています。

会見を見ていてカオスを感じたあたりです。
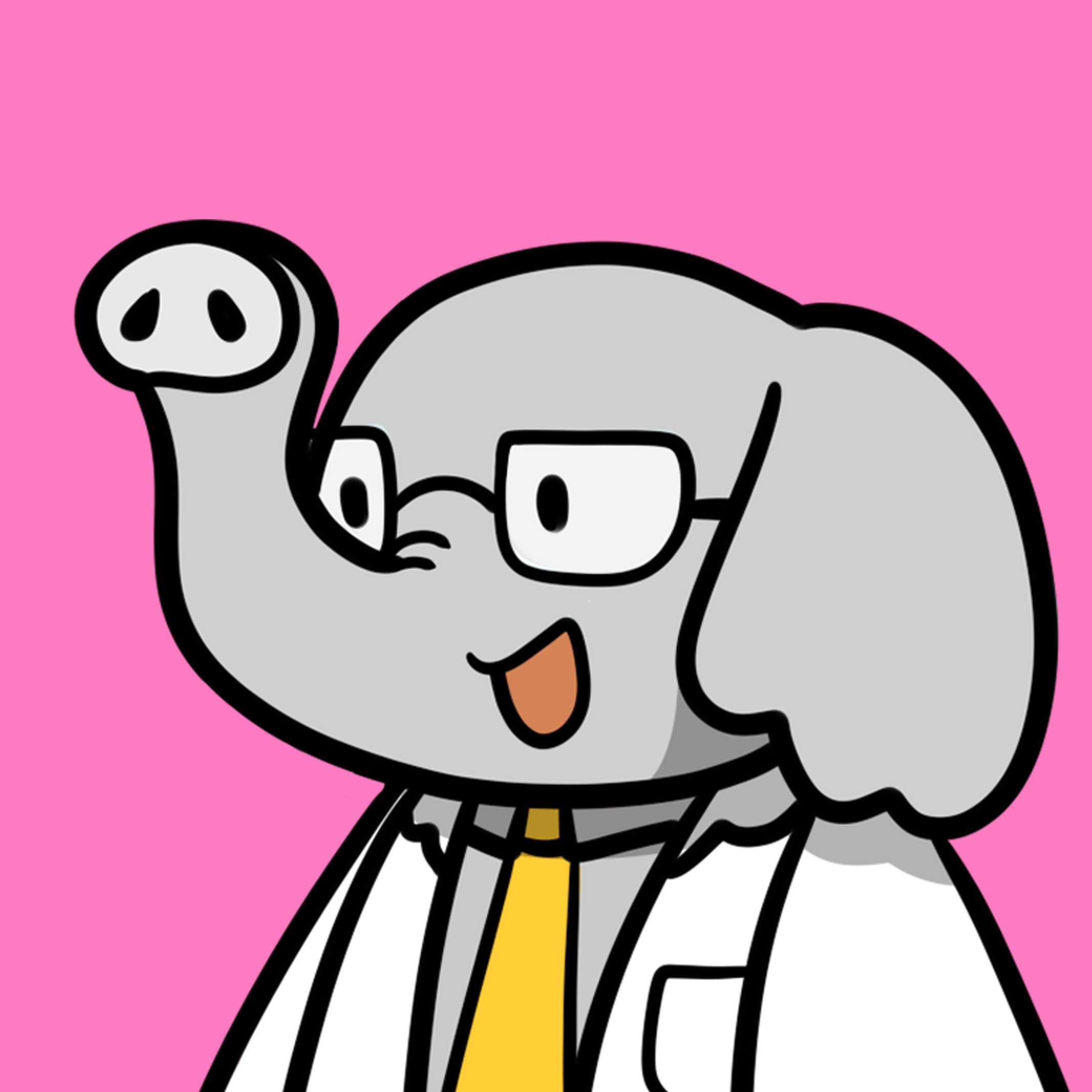
多くの人がそう感じたと思うよ。会議では立場を守りたいね。参加者同士で気をつけられるといいよね。
会議においても時折、場を乱すことが目的の人や流れの主導権を得ようとする人がいます。参加者として、会の目的やルールの範囲内で自分の目的を果たせるよう努めましょう。立場を越えたふるまいは品位を損ねたり、他者からの評価を下げたり、不必要に敵を増やすことにつながります。
司会者の選抜と進行スキル
続いて司会者の技量です。他の記事でご紹介したこともありますが、
● 会の進行役となる司会という役割
● 話し合いを上手に進めていくファシリテーターという役割
これらは似ていますが、違った技量になります。会見の冒頭で、決められたプログラム上の挨拶や登壇者の紹介などを一つ一つ進めていくには司会の方は役割を果たすことができていたように見えます。
ですが、臨機応変にその場をコントロールしていくファシリテーターという役割としては、今回担われた方の技量が不足していたと考えられます。また、技量不足を増大させてしまう1つの理由に司会進行役がフジテレビ組織内の人間だったと言うこともあります。
「謙虚に誠意を示さなければいけないフジテレビ」というマイナス評価の前提を背負った状態で場をコントロールしようとしていたわけです。
そうなるとどうしてもルールから逸脱した参加者に対して強制力を発動することに躊躇が生まれます。今回は会見だったので、意見のやりとりに介入する必要はありませんが、場のコントロールは必要です。

場のコントロールに適切な人材はいなかったんですかねぇ。
フジテレビともなると、できる人がいそうな気もしますが。
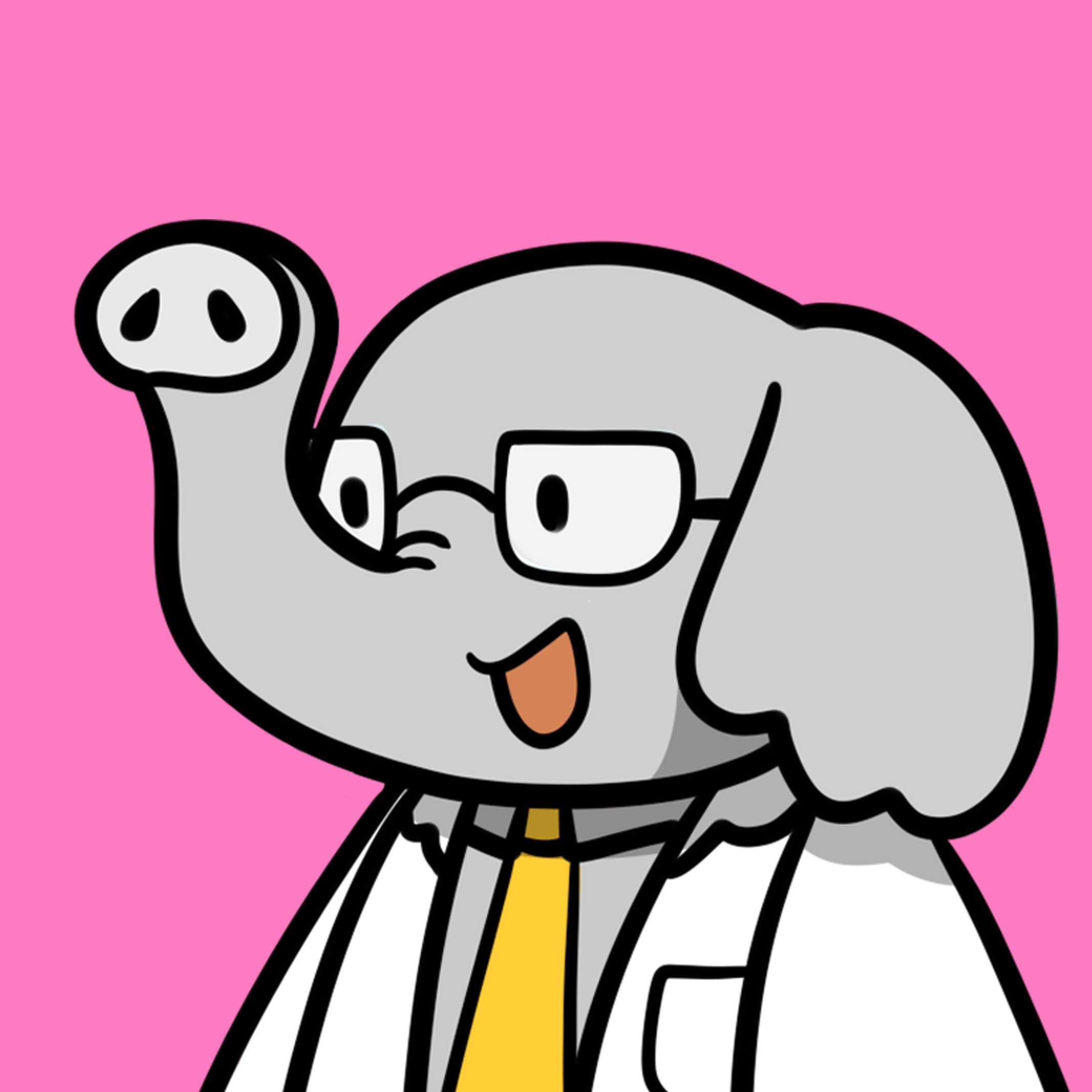
どうだろうね。想像の域をでないな。勘ぐれば、あえて場の混乱を凌ぐ姿勢を見せたかったとも考えられるしね。

敢えて場の混乱が必要ですか?
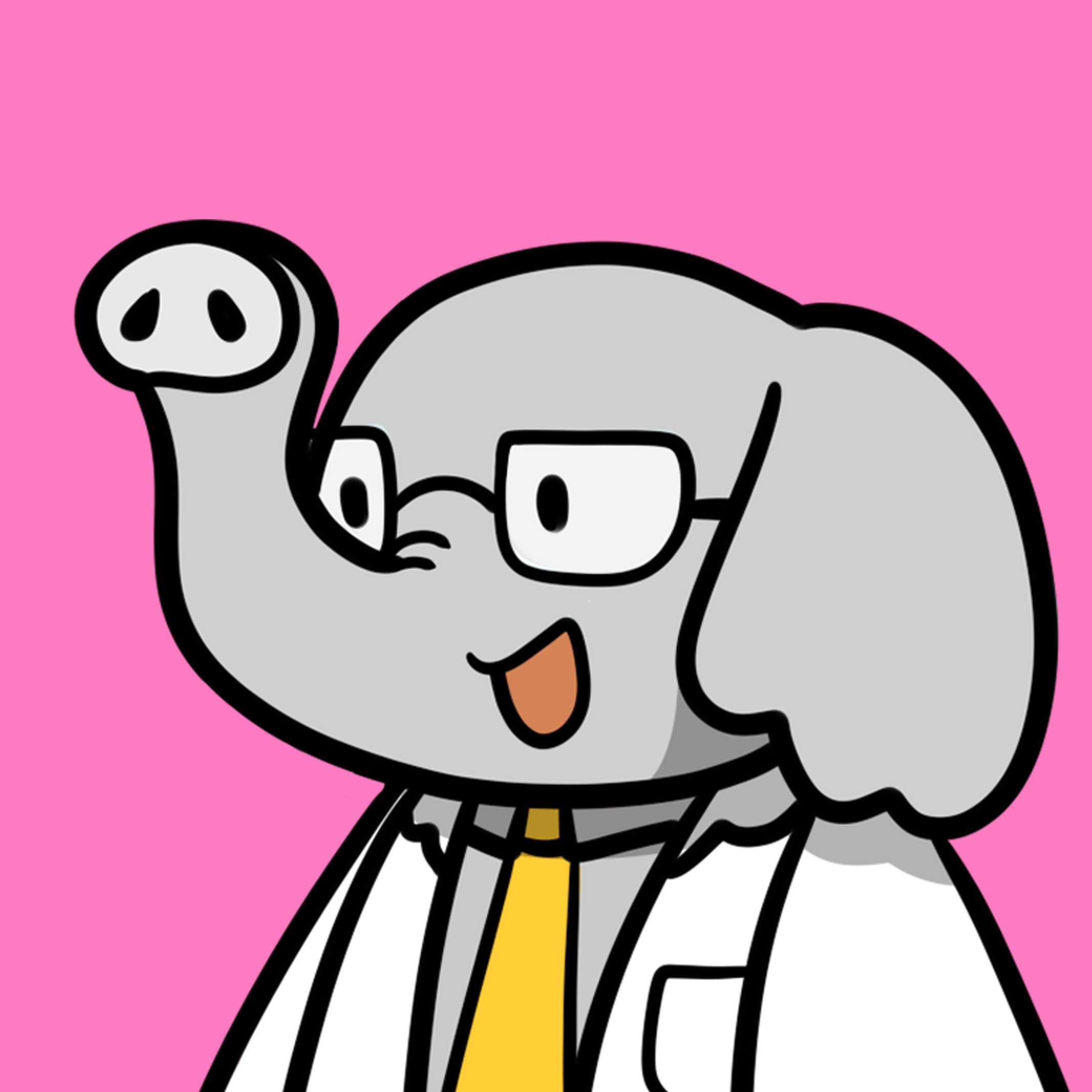
んー、視聴者の注目を核心部分の話題に集中させない結果になったよね。
登壇者が社会的に罰を受けている、禊の見え方にもなったかな。まぁ、スポンサーや株主が納得するには及ばなかったようだけど。
会議で意図的に混乱を作る必要があるのかというと、それはまた別の話題になるかな。

意味深ですね~。
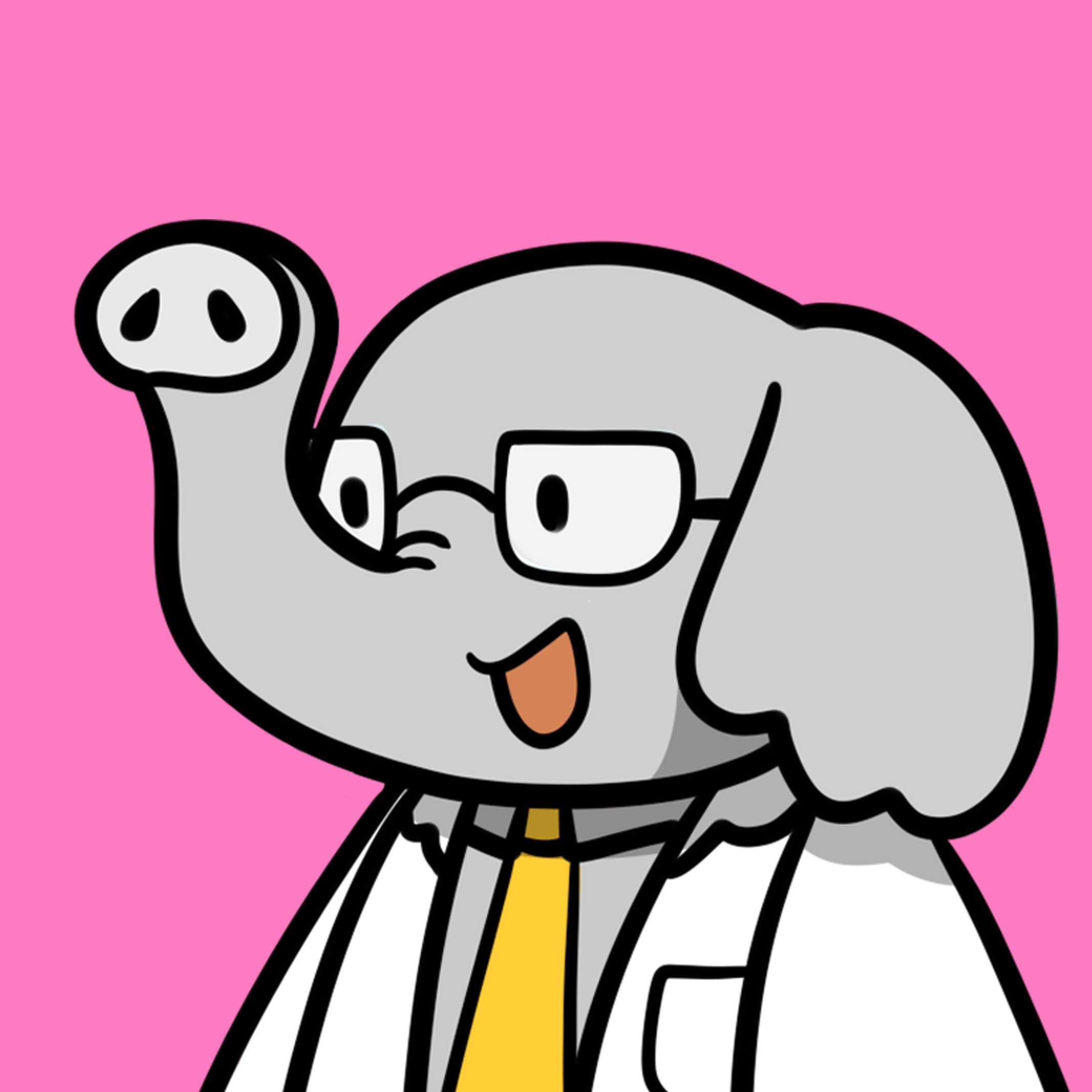
また今度ね。
理想的には司会進行役は中立な立場の人がやることが望ましいです。ですが、今回の会見やその他の会議ではどうしても決められた人員で開催することになるので、中立の立場の人を呼ぶことが難しいことになると思います。
であるならば、中立な立場を念頭において場に介入できる人を選ぶと良いです。開催の冒頭で
「発言者の選択は中立性を念頭に私が担います」
と言うことを明確に宣言する必要がありますし、
「ルールを守れない人はご退場いただくこともあります」
などと最初にルールを設定して、参加者全員が同意の上で望むということで荒れることを抑えられるでしょう。
会議に当てはめると、司会の進行に添わないふるまいや円滑な意見交換を乱すと判断された場合にはご退場いただくこともある、と事前に合意の上で開催する。
中立性を踏まえた進行ができる人を可能な限り選抜し、司会を担ってもらう。
その他司会としての具体的な手法
- あらかじめルールを決め、それを宣言し、みんなで合意をした上で始めるように、会議の前に一定のルールを決めておくことをグラウンドルールといいます。割と一般的な手法でもありますので、どんなグラウンドルールが良いのかは検索してたたき台を見つけてもいいと思いますし、ご自分でオリジナルのものを作って試してみてもいいと思います。
- 会の目的など暗黙の前提を引き合いに出し、問いただす介入ができます。
「あなたの真摯な姿勢が他の参加者の手本になります」
「進行の妨げになり、他の質問者の時間を奪っていますのでご退場ください」
質問者ができること
では質問者の立場で良い質問の仕方を具体的にどんなアイディアが考えられるか展開してみたいと思います。ルールを守り制約の中でそれでも必要な情報を相手から聞き取りたい場合にどういうことができるでしょうか。
前述のルールを守らない人たちの言動や振る舞いは、視聴者の多くが嫌悪や落胆の視点で見ていたようです。ですが一方で、プライバシーの鑑定や人権と言う観点から具体的な話をなかなか発言しない相手に不満が出る気持ちも理解はできるのではないでしょうか。
とは言え、こちらの主張を投げつけて、相手の考えを引き出そうとしても明確なレスポンスは得られません。ましてやそれをさらにこじ開けようと感情を乗せても構図として相手が優位にならざるをえません。
アイディアの1つとして有効なのは、大義に照らし合わせるということです。ここで言う大義とは、活動の根底にある概念や順守すべき対象のことで、今回の会見では株主や法律(例えば放送法)です。
ですので、そういったものを引き合いに出し、今回の出来事を照らし合わせてどう解釈するのか、自分なりの言葉で答えてもらう投げかけができ、その返答次第で次の議論に進むことができます。
構図でいうと、質問者 vs 回答者ではなく、大義 vs 回答者そして、観察視点の質問者となります。すると質問者の意見に答えるということではなく、対義に対して答えると言う構図ができますので、相手はより言葉を尽くさなければいけない状況が作れます。
質問の例としてはこんな感じです。
「今回の件を株主に説明する場合、どのように説明しようと思いますか?」
とか、
「放送法の第何条を読み上げた上で今回の件を照らし合わせてあなたなりの解釈を聞かせてください。」
となります。
会議で、意見交換が紛糾した時や、オープンでない姿勢を示す参加者に対しては、会の目的、議論の目的、組織の理念、ルールなどを引き合いに出し、どのように考えるのか投げかけてみましょう。
本質的な目的
会見以降も、さまざまなリーク、憶測、解説動画などが出ており事態そのものは落ち着くまで時間がかかりそうです。
取り沙汰されている論点や問題に敢えて踏み込まず、本質的な目的は何か考えてみたいと思います。つまり相談役の権力やタレントの過ち、日本のマスメディア、どんな視点で今回の事態を見つめたらいいかという事になります。
人が悪いのか、環境が人を悪くしたのか
一旦、話が飛躍してしまいますが、かつて天動説が信じられていた社会では地動説をとなえる学者が処刑になった歴史があります。今では考えられません。
人々の価値基準が主として宗教だったので、徐々に哲学や科学が発達する中で、新しい視点が受け入れられていく過程として起こったこととなります。
そして、テレビが日本メディアの全盛期だった時代は、人々の基準としてフジテレビの風習は「良」とされていたと言えます。ですが、今となっては人々の基準が変わり「それまでは通用してきた」こととして議論を巻き起こしていると見ることができます。
時代の変遷で、その都度人々が物事を見定めるレンズは変わりうるのが原則のように感じます。
同様に歴史を見ると共通項としてあるのは「権力の暴走」です。人はいつの時代も、より良くなるために影響力を育て、大きく育った影響力が権力としてやがて暴走し腐敗を生んでいます。
今回のフジテレビのさまざまな事態は、個人の責任によるところはあるのかもしれませんが、同時に個人が集まり、集団環境を作りその環境によって個人が権力に溺れてしまったと捉えることもできます。
権力に溺れる理由は、人の弱さかもしれません。タガが外れてしまう弱さであり、SNS上の誹謗中傷もある種の人の弱さではないでしょうか。
当研究所なりの解釈
改めて本質的な目的を考えると、個人の責任、組織の責任などを越えて、権力の暴走を人の手でどうやったら抑えられるのかであり、できるかぎり未来長きにわたり有効な手段を見出せるか、という事ではないかと考えられます。ただ、同時に歴史的に都度権力は暴走してきたので、未来でも暴走の可能性が捨てきれないところも考えられます。
実際の会議では、目の前の問題や課題を乗り越えるために議論が展開されることがほとんどと思われます。ですが、より本質的な議題に向き合っていくことも会議を展開する組織そのものの成長に欠かせないのではないでしょうか。少しの時間を割いてでも話し合ってみると思いがけないブレイクスルーが生み出せるかもしれません。
フジテレビが現在の混乱を招かないシナリオがあったのだとすれば、上記のような議題を会議で話し合う必要があったのではないでしょうか。
さて、目の前の課題に向き合うか、本質的な課題に向き合うか、このバランスはどうしらた良いものでしょうか。置かれた状況によることもあるかと思いますが、まず、課題を見定めるノウハウを1つご紹介しておきます。
スティーブン・R・コヴィー著 「7つの習慣」 の中にあるタイムマネジメント法です。
緊急度が高いか、低いか、重要度が高いか、低いかという2軸で物事を整理することができます。この時、本質的なものは、緊急度が低いが、重要度が高いところに分類されます。本質的な問題や課題が保留にされ続けると、緊急度も高い状況になった時に大変になったり、取り戻せなかったりするようです。会議では時折参加者一同で、課題に緊急度、重要度を当てはめ、どれに向き合うか議論してみてはいかがでしょうか。
会議では、議題の中に目の前の課題だけでなく、重要な課題も取り入れましょう。どれが重要な課題かは参加者同士で考えることをおススメします。



コメント